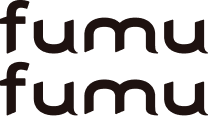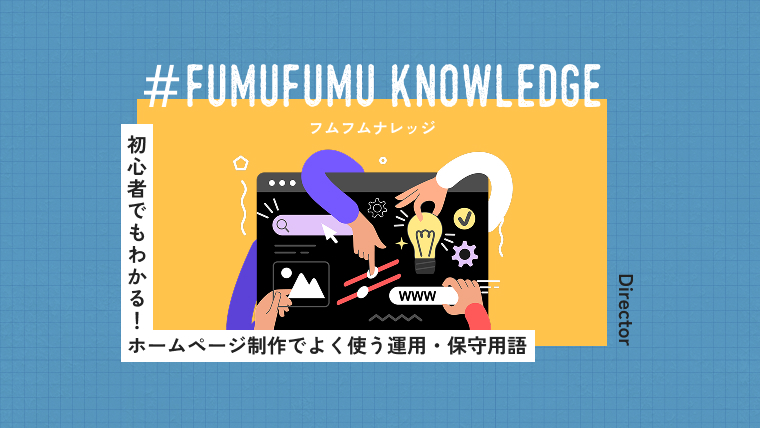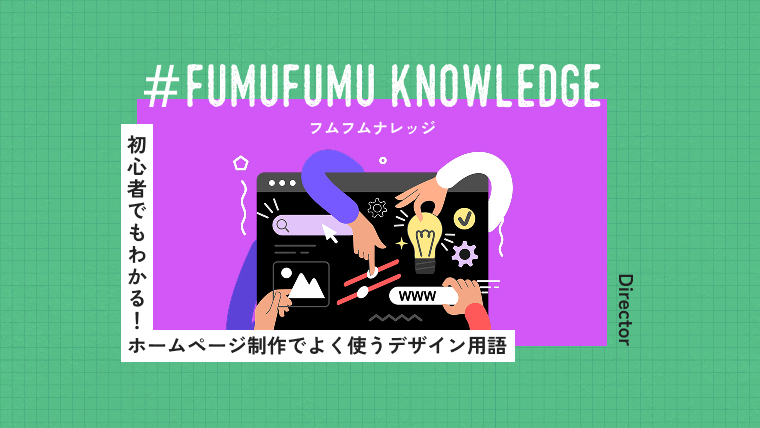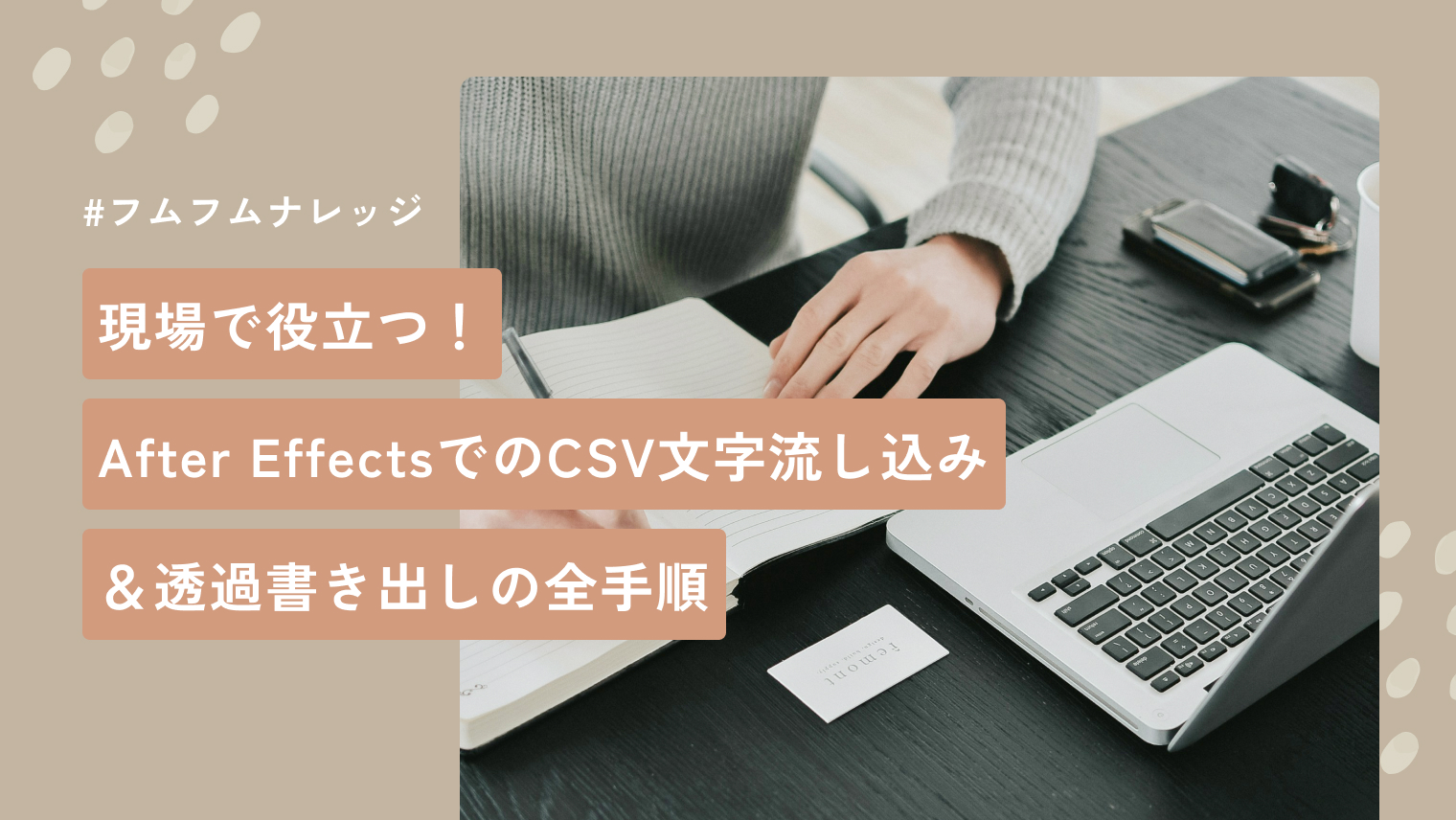コーポレートサイトの運用やリニューアル後の保守を担当することになったけれど、「専門用語が多くて調べながらでないと会話についていけない…」と感じていませんか?
このページでは、ホームページの運用や保守に関わる業務や打ち合わせでよく使われる用語を、50音順でわかりやすく解説。
「運用・保守用語編」として、ホームページの運用・保守に関する用語をご紹介します。
あ行
アクセス解析
Webサイトへの訪問者数や行動をデータとして可視化する仕組み。改善のヒントを得るために欠かせません。
アップデート
CMSやプラグインなどのソフトを最新版に更新すること。セキュリティ向上や機能追加のために行われます。
アナリティクス
Googleアナリティクスなど、アクセス解析ツールの総称。訪問数やページ閲覧数などを分析します。
アクセシビリティ
誰でも情報にアクセスしやすい設計。高齢者や障がい者にも配慮したWebサイト構築に重要です。
インシデント対応
トラブルや障害が起きた際の初期対応。迅速な対処が信頼維持に直結します。
インデックス登録
Googleなどの検索エンジンにページが認識・登録されること。適切なSEOの基本要素です。
運用マニュアル
Webサイトの更新方法や管理ルールをまとめた資料。担当者が変わっても安定運用できるように備えます。
SEO(Search Engine Optimization)
検索エンジン最適化。Google検索などで自サイトが上位表示されるための仕組みや改善手法です。
MEO(Map Engine Optimization)
Googleマップ検索で会社や店舗が上位に表示されるよう行うローカルSEO対策です。
XMLサイトマップ
検索エンジン向けにURL一覧と更新頻度情報を整理したファイル。クローリングの効率に関わります。
か行
解析ツール
Webサイトの状況を分析するツール全般。Googleアナリティクスなどが代表的です。
カスタマーサポート
ユーザーからの問い合わせや不具合に対応する窓口。信頼されるサイト運営に欠かせない要素です。
管理画面
Webサイトの設定や更新を行うための専用画面。CMSでは主にこの画面で作業します。
キャッシュ
一度読み込んだデータを一時的に保存する仕組み。表示速度の向上などに利用されます。
キャッシュクリア
一時的に保存されたデータを削除し、最新の情報を反映させる操作。表示トラブル解消に有効です。
緊急対応フロー
サーバートラブルや改ざんなど、緊急時の対応手順。予め準備しておくと迅速な対応が可能です。
クレジット表記
著作権情報や制作会社の名前を記載すること。サイトの下部に小さく表示されることが一般的です。
クローラー
検索エンジンがWeb上の情報を収集するロボット。適切なSEOにはクローラーへの対応も必要です。
KPI(ケーピーアイ)
目標達成のための重要指標。アクセス数やCV率などを指標に運用効果を測定します。
検索クエリ
ユーザーが検索エンジンに入力する言葉。流入経路の分析やSEO対策に役立ちます。
検証環境
本番公開前に動作確認を行うための仮のサイト。変更の影響を事前にテストできます。
コンバージョン(CV)
資料請求や問い合わせなど、目的となる成果の達成を指します。
さ行
サイトマップ
サイト全体の構成を示す一覧。ユーザーや検索エンジンがページを把握しやすくなります。
サーバー監視
Webサイトが正常に動いているかを自動でチェックする仕組み。障害の早期発見に役立ちます。
再リリース
不具合修正や機能追加のために、修正後のデータを再び公開すること。慎重な確認が必要です。
CMS(コンテンツ管理システム)
WordPressやDrupalなど、専門知識がなくても更新できるシステム。運用効率を格段にアップします。
システム保守
Webサイトの仕組みが正常に動くようにするための点検や修正作業。定期的な対応が必要です。
システムログ
ユーザーの操作履歴やエラー情報などの記録。トラブル時の原因調査に活用されます。
シナリオ設計
ユーザーがWebサイトでどのように行動するかを想定して設計するプロセス。コンバージョン率にも影響します。
常時SSL化
サイト全体をhttpsで保護するセキュリティ対策。ユーザーの安全性と信頼性の向上につながります。
承認フロー
複数の担当者で内容をチェック・承認する手順。ミスを防ぎ、情報公開の質を高めます。
障害報告
サイトが停止・不具合を起こした場合の報告書。原因や対応状況を明確にすることで信頼を保てます。
セキュリティ対策
ウイルス感染や不正アクセスからサイトを守る対応。運用保守における必須項目です。
た行
タグマネージャー
Googleタグマネージャーなど、計測タグの管理ツール。アクセス解析や広告の設置が簡単になります。
ダッシュボード
各種データや指標をひと目で確認できる画面。サイト状況の把握に便利です。
直帰率
1ページだけ見てサイトを離れた割合。高い場合、コンテンツの適用ミスマッチや操作性の問題が疑われます。
追加改修
既存サイトに新しい機能やコンテンツを加える作業。定期的な見直しで鮮度を保ちます。
定期メンテナンス
サーバーやCMSの更新、不具合の確認などを定期的に実施。安定した運用に必要な作業です。
テストアップ
修正や新コンテンツを仮環境で反映し、問題がないか確認する工程。リリース前の重要なプロセスです。
テスト環境
本番公開前に動作確認を行う専用の環境。リスク軽減に欠かせません。
導線設計
ユーザーが目的のページにたどり着きやすくするための構造設計。成果につながる運用の鍵です。
トラッキングコード
アクセス解析や広告計測のために設置するJavaScriptコードです。
トラフィック分析
訪問者数や流入経路などの動きを把握する解析。改善ポイントを見つける鍵となります。
な行
内部リンク
同一サイト内の他ページへ誘導するリンク。SEOや回遊性向上に効果的です。
ナビゲーションメニュー
ユーザーが情報にたどり着きやすくするための案内メニュー。UI改善に欠かせません。
納品形式
修正データや資料の受け渡し形式。ファイル形式の指定が必要な場合もあります。
入稿データ
テキストや画像など、更新に必要な素材データ。フォーマット統一が重要です。
任意項目
フォームなどで、入力が必須ではない情報項目。ユーザーの負担を軽減します。
は行
バージョン管理
コードやデータの変更履歴を記録・管理する仕組み。更新の安全性を高めます。
バックアップデータ
復元用として保存されたサイトやサーバーの情報。トラブル時の備えに欠かせません。
PDCA
「計画→実行→評価→改善」の継続的な改善サイクル。Web運用の基本指針です。
表示崩れ
ブラウザや端末で意図したレイアウトにならない状態。CSS調整などで修正します。
表示速度改善
サイトの読み込み時間を短縮する対策。ユーザー満足度やSEOに直結します。
フォーム改善
入力フォームの設計を見直し、離脱防止やCV率向上を図る施策です。
分析レポート
アクセス状況やユーザー行動をまとめた資料。改善案の根拠に使用されます。
フォローアップ
納品後のサポートや追加対応のこと。信頼関係構築に重要です。
ページ更新
新しい情報を反映したり、既存内容を修正すること。運用業務の基本です。
ま行
マニュアル整備
CMS操作や更新ルールの手順書を用意すること。社内の属人化を防ぎます。
メールサーバー
フォーム送信や通知メールの処理を担うサーバー。送信トラブルの原因にもなりえます。
メンテナンスモード
一時的にサイトを非公開にして、更新や修正を行う状態。作業中の誤表示を防ぎます。
メタ情報
ページのタイトルや説明文など、検索エンジンに伝える情報。SEO効果に関係します。
モニタリング
サイトの稼働状況を常に監視すること。障害を早期発見できます。
や行
ユーザーテスト
実際の利用者による操作確認。UI/UX改善の有力な手段です。
ユーザーテスト
実際の利用者に使ってもらい、使いにくさや改善点を見つける検証方法。UI/UXの改善に活用されます。
ら行
リダイレクト設定
旧URLから新URLに自動で転送する仕組み。リニューアル時などに使用します。
リカバリープラン
障害発生時の対応手順を定めた計画。事業継続の備えとして必須です。
ログイン権限
CMSや管理画面へのアクセス制限。ユーザーごとの操作管理に必要です。
ロールバック
更新後に問題が出た場合、以前の状態に戻すこと。安全な保守運用に欠かせません。
ログ解析
アクセスログを分析し、ユーザーの動きを可視化。改善策のヒントが得られます。
わ行
WAF(Web Application Firewall)
不正アクセスや攻撃からサイトを守る防御システム。セキュリティ強化に欠かせません。
ワークフロー管理
更新作業の申請から承認までの仕組み。ミスや漏れを防ぐための流れを整理します。
ホームページの運用や保守には、聞きなれない言葉がたくさん登場します。
はじめて担当される方にとっては、不安や戸惑いもあるかもしれません。
でも、よく使われる用語を少しずつ理解しておくだけで、やりとりがしやすくなり、日々の業務にも自信が持てるようになります。
この「運用・保守用語編」が、ホームページをしっかりと育てていくための頼れる味方となれば嬉しいです。