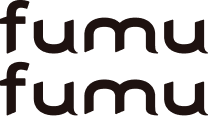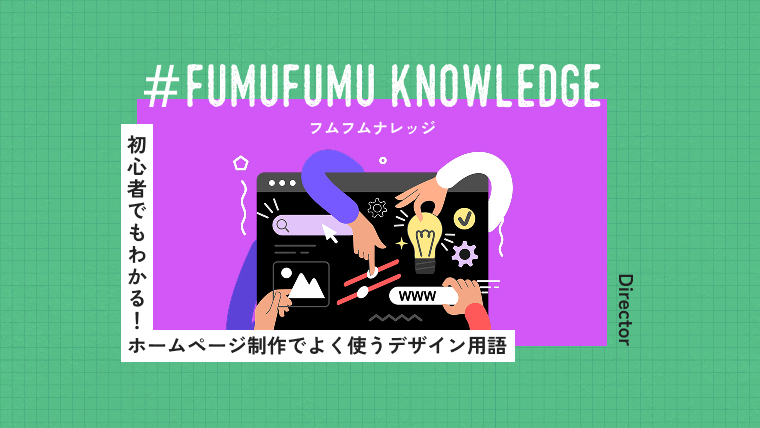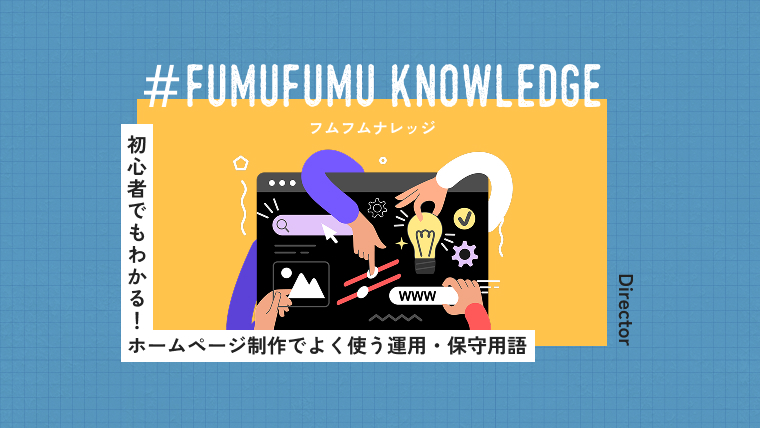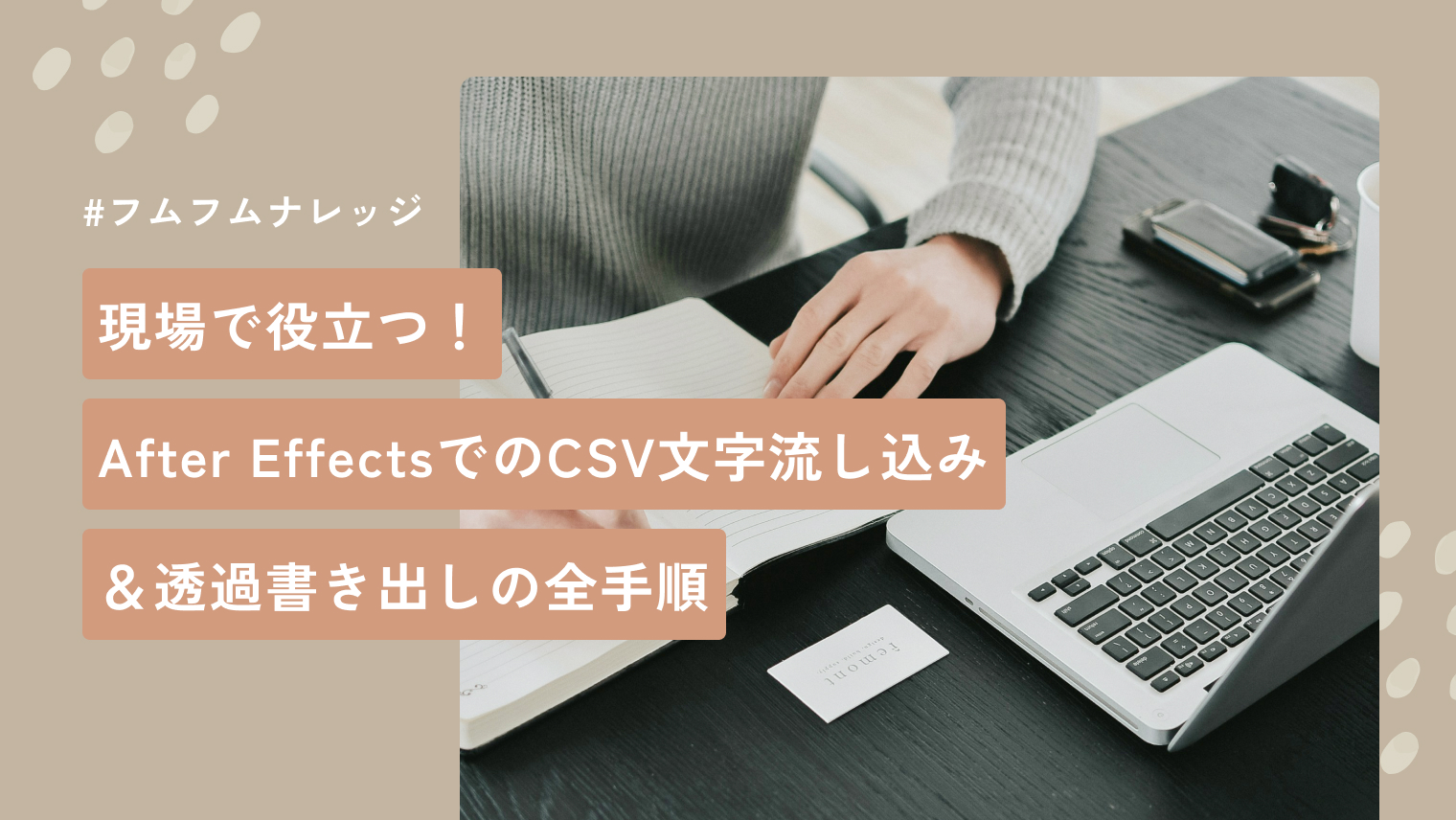コーポレートサイトのリニューアルや新規制作を担当することになったけれど、
「専門用語が多くて話についていけない…」と感じていませんか?
このページでは、ホームページ制作やリニューアルに関わる打ち合わせでよく登場する用語を、50音順でわかりやすく解説。
今回は「デザイン用語編」として、デザインに関するの用語をご紹介します。
あ行
アイキャッチ画像
記事やページの冒頭に表示される注目を集める画像のことです。内容を視覚的に伝える役割があり、ユーザーの興味を引きやすくなります。
アニメーション
文字や画像に動きを加える表現技法です。視線を誘導したり、操作のヒントを示したりするのに役立ちます。適度な使用がポイントです。
アスペクト比
画像や動画の縦横の比率を表します。たとえば「16:9」などで指定され、画面にきれいに収めるために重要です。
アバウトページ
会社やサービスの概要を紹介するページのことです。企業の理念や信頼感を伝える場として大切にされています。
アンダーライン
文字の下に引かれる線を指します。リンクであることを示したり、強調に使われたりしますが、多用には注意が必要です。
アウトライン
見出しの構造や情報の骨組みを整理する考え方です。読みやすく、論理的なページを設計するための基礎になります。
アートディレクション
全体のビジュアルやコンセプトの方向性を統括する役割です。デザインの一貫性と品質を保つために重要です。
アセット
Webデザインに使う画像・フォント・アイコンなどの素材全般を指します。プロジェクトごとに整理して管理します。
アクセントカラー
デザイン全体の中で、特に目立たせたい要素に使う差し色です。行動を促したいボタンなどに使われることが多いです。
アライメント
文字や画像などの配置の整え方を指します。「左揃え」「中央揃え」などがあり、統一感や読みやすさに影響します。
か行
カラーコード
色を表す6桁の英数字(例:#FF9900)のこと。Web制作では正確な色指定に使われます。ブランドカラーの管理にも重要です。
カラム
ページの縦の区切り(列)を指します。1カラム(1列)や2カラム(2列)など、レイアウトの基本構成を決める単位です。
カルーセル
複数の画像やコンテンツをスライド表示できる仕組みです。限られたスペースで複数情報を見せたいときに便利です。
キービジュアル
ページの最上部などに配置される印象的な画像や動画のこと。サイトの第一印象を左右するため、丁寧に作り込まれます。
キャッチコピー
ページの冒頭に配置される短いメッセージです。訪問者に印象づけたり、サービスの特徴を端的に伝えるために使われます。
グリッドデザイン
縦横の線(グリッド)で要素の位置を揃える設計手法です。視線の流れを整え、洗練された印象を与える効果があります。
グラデーション
色がなめらかに変化する表現方法。背景やボタンに使われることが多く、奥行きや動きを感じさせます。
コンテナ
ページ内の内容をひとまとまりとして包む領域を指します。画面サイズに応じて自動的に幅が調整されることもあります。
コンポーネント
デザインの中で繰り返し使われる部品のこと。ボタンやカードなど再利用可能な要素として管理されます。
さ行
サイドバー
ページの横に設置される補助的なエリア。最新記事やバナー、メニューなどを表示して回遊性を高めます。
サムネイル(サムネ)
一覧ページやSNSなどで表示される小さな画像。元の画像やページ内容の概要を視覚的に伝える役割があります。
サムネイルリンク
画像をクリックすると別ページへ移動する仕組み。ギャラリーや一覧ページでよく使われます。
サブカラー
メインカラーを引き立てる補助的な色。デザインに調和やアクセントを加えるために使われます。
サブビジュアル
メインビジュアルに続く補足的な画像エリア。コンセプトの補完やコンテンツ導入部として設けられることがあります。
スクロール
スマートフォンやタブレットなど、異なる端末でも快適に閲覧できるようにデザインを自動調整する仕組みです。
スマホ対応(レスポンシブ対応)
スマートフォンやタブレットなど、異なる端末でも快適に閲覧できるようにデザインを自動調整する仕組みです。
スライダー
画像やテキストが自動または手動で切り替わるパーツ。キャンペーンやサービス紹介などで多く使われます。
セクションタイトル
各コンテンツの区切りに置かれる見出し。情報の構造を明確にし、読みやすさを高めます。
センター配置
要素を左右中央に配置するデザイン手法。バランスがとりやすく、安定感のある印象を与えます。
た行
タグライン
企業やサービスの特徴・価値を短い言葉で表現するキャッチフレーズ。ブランドイメージを伝えるために使われます。
タイトル画像
ページタイトルと一緒に配置される代表的な画像。ビジュアルと文字を組み合わせて印象づけることが目的です。
テキストリンク
文章の中に組み込まれたリンク。ユーザーに自然な形で別ページへの移動を促します。
デザインカンプ
完成形に近い見た目のデザイン見本。クライアントへの確認や開発時の指示に用いられます。
テンプレートデザイン
あらかじめ用意されたデザインパターン。コストや工数を抑えつつ、統一感のある制作が可能です。
トップページ
サイトの最初のページ。訪問者の第一印象を決めるため、情報設計とビジュアルのバランスが重要です。
トンマナ
トーン&マナーの略。デザインや文章の雰囲気・方向性を統一するための方針を指します。
ドロップシャドウ
要素の下に影をつけるデザイン手法。立体感を出したり、視認性を高める効果があります。
トグルボタン
クリックやタップで表示・非表示を切り替えるボタン。FAQやメニューなどで活用されます。
トリミング
画像の一部を切り抜いてサイズや構図を調整すること。見せたい部分だけを強調できます。
な行
ナビゲーション
ページのどこに何があるかを案内するメニューのこと。サイトの使いやすさに直結します。
ナンバリング
項目に番号を振ることで、順序や優先順位を明確に示す手法です。説明や比較にも役立ちます。
2カラムデザイン
2列構成のレイアウト。主に「メインコンテンツ+サイドバー」の組み合わせで使用されます。
ニュートラルカラー
主張が少なく他の色と調和しやすい色。背景やベースに使われることが多いです。
日本語フォント(和文フォント)
日本語で表示するためのフォント。読みやすさ・印象・雰囲気に大きな影響を与えます。
入稿データ
画像や原稿など、Web制作に必要な素材を制作会社に提出するファイル一式のことです。
認知負荷
ユーザーが情報を理解する際にかかる負担。整理されたデザインでこれを軽減することが重要です。
ネガティブスペース
意図的にあけた余白。デザインを整えるだけでなく、視線誘導にも効果があります。
ネスト構造
要素の中に要素を重ねて構成するデザイン手法。複雑な情報を整理して伝える際に使われます。
は行
配色パターン
色の組み合わせのルールや見本。印象や視認性を左右するため、慎重に選定します。
ハンバーガーメニュー
スマホサイトでよく見られる、三本線のメニューアイコン。押すとナビゲーションが表示されます。
パディング
要素の内側に確保された余白。文字や画像との間隔を調整するのに使います。
バナー画像
広告や告知を目立たせるためのリンク付き画像。クリックを促すことが目的です。
ビジュアルヒエラルキー
情報に視覚的な優先順位をつける考え方。重要な情報を目立たせ、伝わりやすくします。
フォントサイズ
文字の大きさを指します。見出しや本文のバランスを取ることで読みやすさが向上します。
フッター
ページの一番下に表示される共通エリア。会社情報や著作権表記、ナビゲーションなどを含みます。
フルスクリーンデザイン
画面全体を使ってコンテンツを表示するデザイン。印象的で没入感が高まります。
ブレイクポイント
画面サイズごとにデザインを切り替える基準。レスポンシブ対応に欠かせません。
ブロークングリッド
あえて規則性を崩した配置のデザイン手法。ダイナミックで個性的な印象を与えることができます。
ま行
マージン
要素の外側に空ける余白のことです。見た目を整え、読みやすくするために欠かせない基本的な考え方です。
マイクロインタラクション
クリックやホバー時に起こる小さな動きや反応。操作性を高め、ユーザーに心地よい体験を提供します。
マスク
一部だけを表示させる加工技術。画像の一部を円形に切り抜くなど、視覚的なアクセントに使われます。
マテリアルデザイン
Googleが提唱するデザインガイドライン。奥行きや影の使い方で、直感的で操作しやすいUIを目指します。
マルチカラムレイアウト
3カラムや4カラムなど、複数列で情報を並べる構成。整理された印象になり、多くの情報を見やすく配置できます。
マルチデバイス対応
PC・スマホ・タブレットなど、複数の端末で快適に閲覧できるように設計すること。現代のWebサイトでは必須です。
マトリクスレイアウト
縦横に均等に要素を並べた構成。製品一覧や事例紹介など、比較や一覧性が求められる場面でよく使われます。
マーカー装飾
強調したい文字の背景に色をつける装飾方法。文章中で注意を引きたいときに効果的です。
や行
ユーザビリティ
Webサイトの「使いやすさ」のこと。誰でも迷わず操作できるように設計することが重視されます。
ユーザーテスト
実際の利用者に使ってもらい、使いにくさや改善点を見つける検証方法。UI/UXの改善に活用されます。
ユーザーインターフェース(UI)
ユーザーとWebサイトの接点となる画面や操作まわりのこと。見た目と使いやすさの両方が求められます。
ユーザーエクスペリエンス(UX)
利用者が得られる「体験」全体を指します。満足度や印象にも大きく関係します。
余白(ホワイトスペース)
文字や画像のまわりにある空きスペースのこと。読みやすさや落ち着きのあるデザインに不可欠です。
読み込みアニメーション(ローディングアニメーション)
ページや画像を表示するまでの間に流れるアニメーション。待ち時間をストレスなく感じさせない工夫です。
横スクロール
左右にページを移動する操作形式。スマホのギャラリーやスライド形式のコンテンツでよく使われます。
ら行
ランディングページ(LP)
商品やサービスの紹介に特化した1枚構成のページ。訪問者の行動を促すことが主な目的です。
ラベルデザイン
項目名や説明文の見せ方・デザインのこと。入力フォームやナビゲーションのわかりやすさに影響します。
ラフデザイン
完成前のざっくりとしたデザイン案。イメージ共有や初期提案の段階で用いられます。
リード文
見出しの下にある導入文。ページの内容を簡潔に説明し、読む人の興味を引きつける役割を担います。
リキッドレイアウト
画面の幅に応じてコンテンツが伸縮するレイアウト。様々な画面サイズに柔軟に対応できます。
リスト表示
項目を箇条書き形式で整理して見せる方法。比較しやすく、内容をスッキリと伝えたいときに適しています。
わ行
ワイヤーフレーム
Webページの構成や要素の配置を線や枠で表した設計図。デザイン前の構造確認に使われます。
ワンカラムデザイン
1列だけで構成されたシンプルなレイアウト。スマホに適しており、読みやすさを重視した設計に向いています。
ワンポイントカラー
全体の中で一部にだけ使う強調色。視線を誘導したり、ボタンなど目立たせたい要素に使われます。
ワードマーク
企業名やブランド名を文字だけでデザインしたロゴの形式。タイポグラフィを活かした表現です。
ワイドビジュアル
画面の横幅いっぱいに広がる大きな画像。ダイナミックな印象を与え、ファーストビューでよく使われます。
ワークフロー
制作における作業の流れや手順。スケジュールや役割を整理する際の重要な考え方です。
ワイドカラム
通常よりも幅の広いカラム(列)。ビジュアル重視のデザインやLPでよく使われます。
ホームページ制作の現場では、聞き慣れない専門用語が多く登場します。
ひとつひとつの言葉を理解しておくだけで、打ち合わせの安心感や、完成後の満足度がぐっと高まります。
今回ご紹介した「デザイン用語編」が、ホームページ制作のやりとりをスムーズに進めるための一助となればうれしいです。