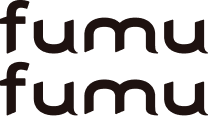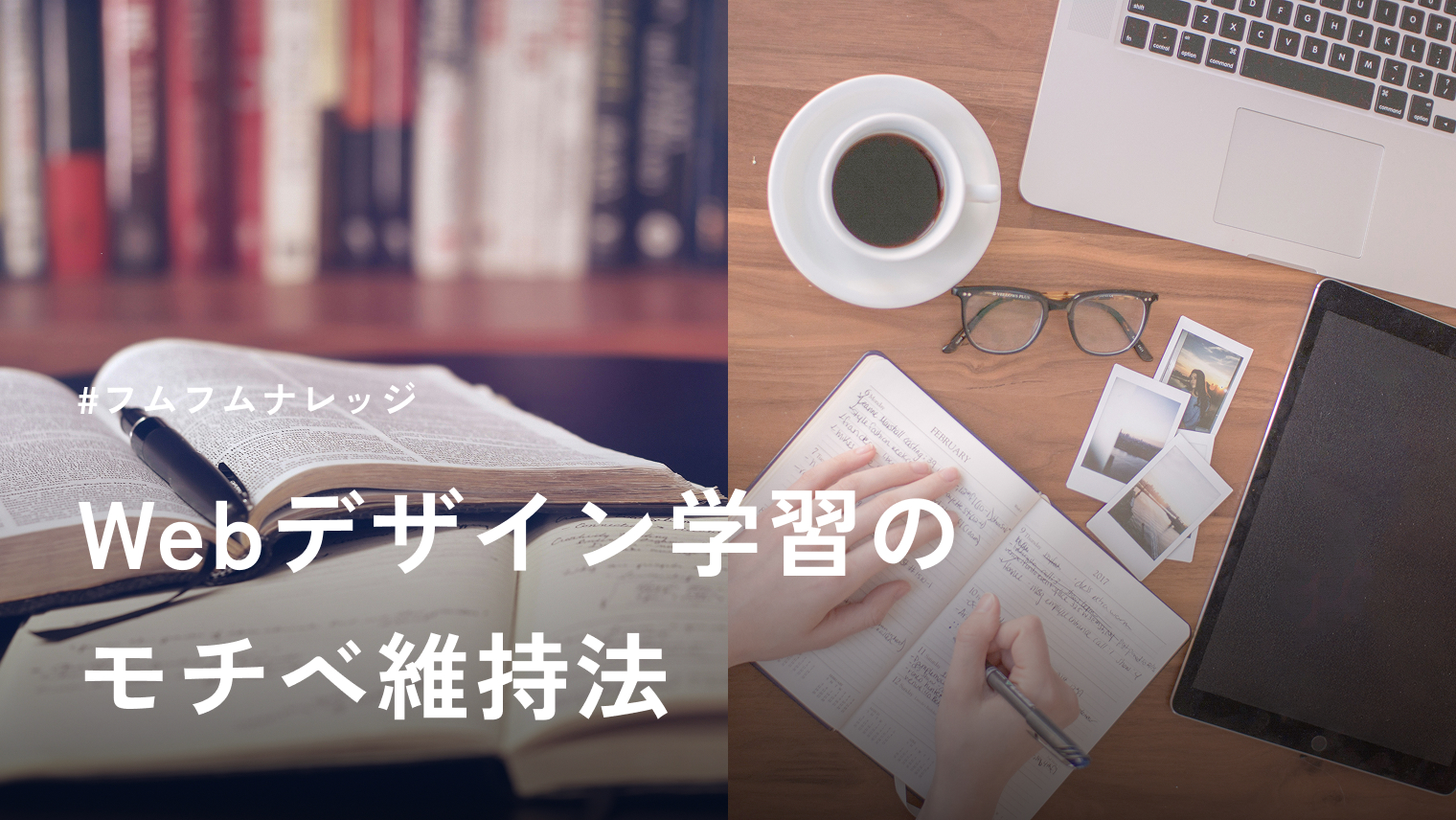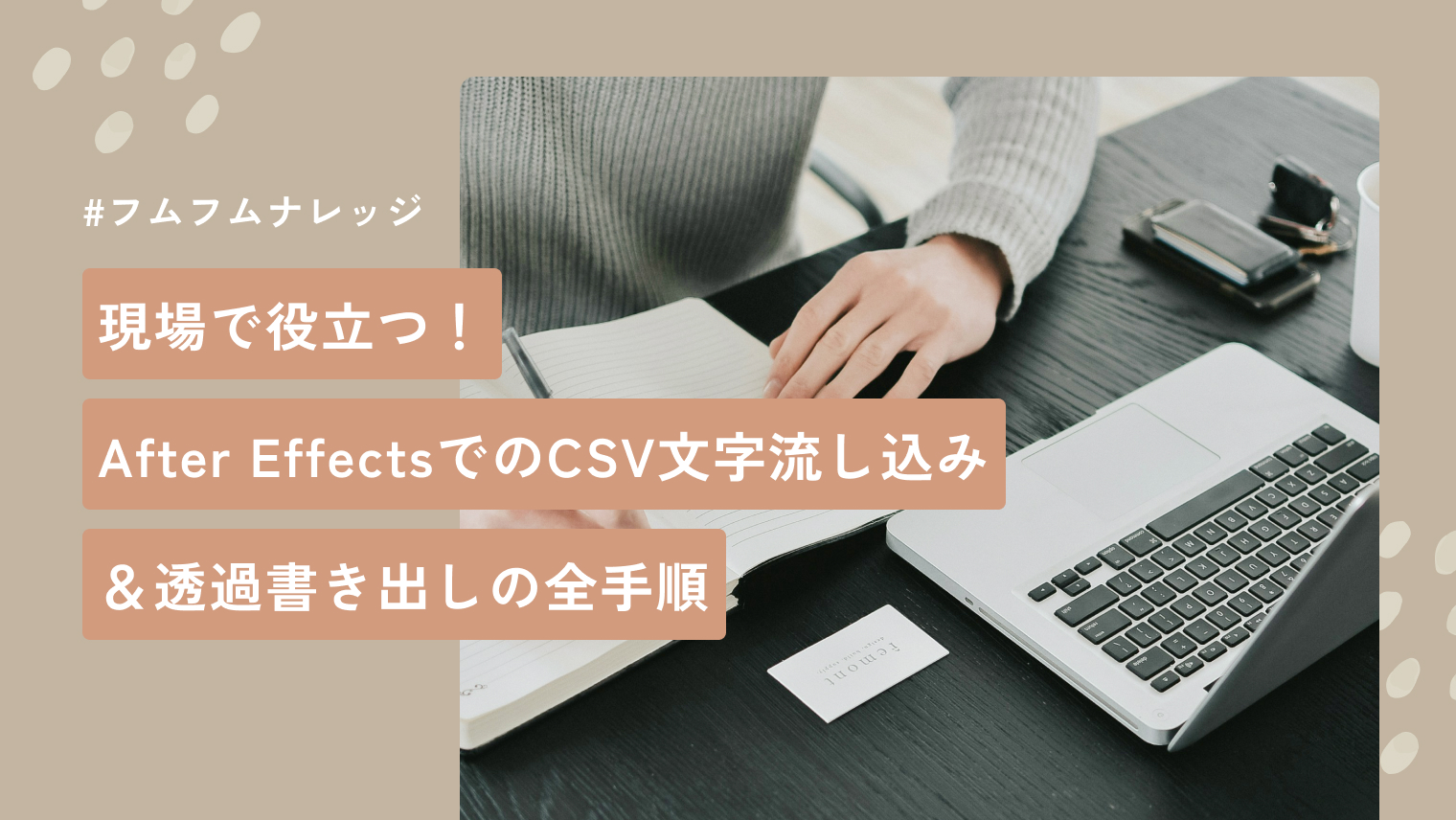「勉強しなきゃ」って辛いとき、ありませんか?
Webデザインの学習を続けていると、「やらなきゃ」という義務感に駆られることがあります。SNSなどを見るとほかの人の進捗が目に入り、自分の現在地と比較して焦りを感じることもあるかもしれません。
わたし自身、過去にそうした焦りから学習計画がうまく進まなかった時期がありました。
この記事では、当時のわたしが試したことの中から、結果的に学習の継続につながった具体的な方法を3つ、個人的な記録として共有します。これが誰にとってもうまくいく方法とは限りませんが、もし同じような状況で悩んでいる方がいれば、何かの参考になるとうれしいです。
1. タスクの最小単位を、極端に小さく設定する
学習初期は、高い目標を設定しがちです。わたしの場合も、「平日は仕事後に2時間コーディング、1時間はデザインを学ぶ」といった計画を立てていました。
しかし、日々の業務で疲れている状態ではこの計画を達成できない日が多く、結果として「今日もできなかった」という自己否定につながっていました。この状態が精神的な負担になり、学習そのものから遠ざかる原因になったと感じています。
そこで、タスクの達成基準を、可能な限り低く設定し直しました。
具体的には、「1日に1行でもコードを書く」「Figmaのファイルを5分間開く」といったレベルです。
この方法の目的は、学習時間を確保することよりも、「今日も学習を中断しなかった」という事実を作ることです。どんなに小さなタスクでもとりあえず完了させるんです。
学習ができなかった日の罪悪感が減り、精神的な負担が軽くなりました。不思議なもので、5分だけのつもりが、集中して30分作業している日もありました。
2. ほかの人の学習状況を、意図的に遮断する
一般的に、学習は仲間と行うことで継続しやすくなると言われます。わたしも当初はオンラインのコミュニティに参加し、SNSでも学習する人たち同士で交流していました。
しかしわたしの場合は、ほかの人の「こんなすごい仕事をした」「新しいスキルを習得した」といった報告が、過度な焦りを生む一因となりました。ほかの人と比較することで、自分のペースを見失いがちだったんです。
そこで、一度すべてのコミュニティから離れ、SNSで学習関連の情報を見るのもやめてみました。
完全に一人で、自分の課題だけに集中する環境を作ったんです。
その結果、周囲の状況に影響されることがなくなり、純粋に「昨日よりできるようになったこと」だけに目を向けられるようになりました。
もちろん、これは個人の特性によるものが大きいと思います。ほかの人と切磋琢磨することでやる気になるタイプの人もいるでしょう。ただ、もしほかの人との比較で疲れてしまっているのなら、いったん「一人になる」という選択も有効な手段の一つかもしれません。
3. 短期的なごほうびを、具体的に設定する
例えば「フリーランスのWebデザイナーになる」といった長期的な目標は、学習の方向性を定める上で重要です。しかし、それだけでは日々の地道な学習を続ける動機として、少し遠すぎることがあります。
そこで有効だったのが、短期的かつ具体的なごほうびの設定です。
例えば、「この参考書の1章を終えたら、少し豪華なお菓子を買う」「一つのサイト模写が完成したら、見たかった映画を見る」といった、ごく個人的なルールを決めていました。
このごほうびは、できるだけすぐに実現可能なものが適しています。「あと30分作業すれば、あれが手に入る」という思考が、学習を継続する直接的な動機になりました。
単純な方法ですが、短期的な目標達成とごほうびを細かく繰り返すサイクルは、モチベーションを維持する上で効果的でした。
まとめ
わたしがWebデザイン学習の継続に困難を感じていた時期に有効だったのは、以下の3つの方法です。
- タスクの最小単位を、極端に小さく設定する
- ほかの人の学習状況を、意図的に遮断する
- 短期的なごほうびを、具体的に設定する
Webデザインのスキル習得は、地道な作業の積み重ねです。学習方法に絶対的な正解はなく、自分自身の特性に合わせて、継続可能な仕組みをつくっていくことが重要だと考えています。
この記事が、学習の進め方に悩む方にとって、一つの事例として参考になればうれしいです。